外国人従業員との対話で起こる誤解とその解消法
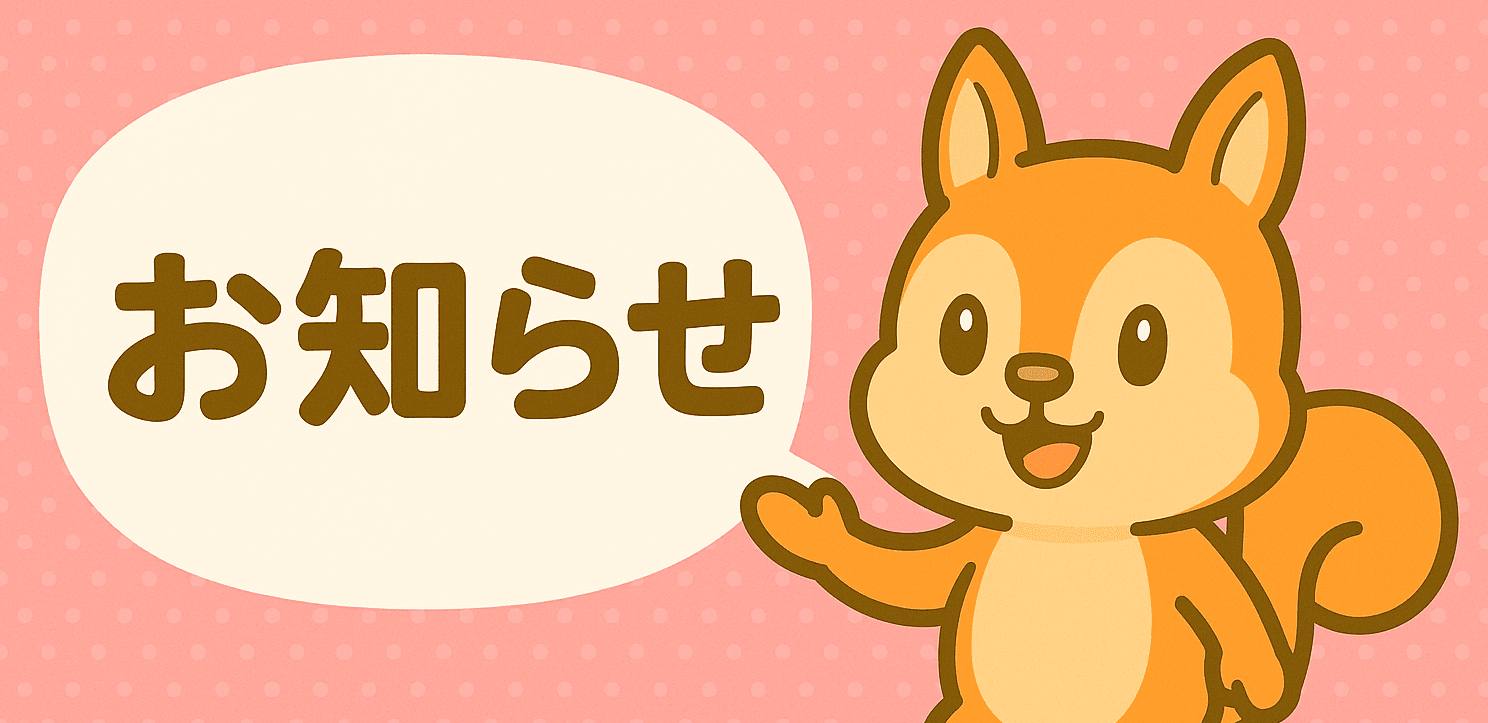
自社に外国人の従業員が在籍していることは珍しくなくなっています。しかし、今なお文化の違いや理解不足で思わぬトラブルが起こるケースも少なくありません。日本の習慣に慣れていない人には何が理解しづらく、受け入れる側にはどんな課題があるのでしょうか。
保険や年金制度の説明は専門家にも相談を
――外国人労働者を雇用する際、言葉や文化の違いからトラブルに発展するケースもあると聞きます。
確かに、入管法が改正されて外国人労働者を多く受け入れ始めた1990年代には、生活習慣の違いなどから各地でトラブルが起こり問題になりました。しかし現在は、日本人から見て「非常識だ」と感じてしまう言動をする外国人は、以前に比べるとずいぶん減っていると私は考えています。諸外国から日本に働きに来る人の多くは、事前に日本語学校や専門学校に通い、言葉や文化・慣習をある程度学んでいる人が増えていますね。
――会社の就労規則や制度についてはいかがでしょう。
社会保険や年金についての説明に苦慮されている企業が多いでしょう。日本のような社会保険制度が整備されている国は少ないので、外国人にとっては理解しにくいのです。制度の理解不足から、悪意なく保険証の貸し借りをしてしまうケースもありました。
病気やケガをした際にすぐに役立つ社会保険に比べ、数十年後の支給を想定する年金はさらに説明が難しい制度です。社労士や税理士などの専門家の力を借りつつ、従業員にきちんと説明できるノウハウを社内に蓄積する必要があると思います。
日本語の難しさがコミュニケーションのストレスに
――制度や法律については、専門家の力も借りて正確に伝えなけれればなりませんね。ただ、来日前に日本語を学ぶ人が増えているのは、企業のスムーズな受け入れにつながりそうです。
ところが、外国からの労働者が一番ストレスを感じるのは、日本語でのコミュニケーションだと言われています。日本語の習熟レベルを測る「日本語能力検定試験」はN1~N5まで5段階のランクがあります。N1は高校生レベル、N2は中学生レベルと言われていますが、日本で生活したことのない外国人にとっては大変難しいものです。日本の大学に留学して日本語を学んだ学生ですら、N1を持っている人にはあまりお目にかかりません。
たとえば「特定技能」という在留資格において、外国人労働者に求められるのは下から二番目の「N4」。「基本的な漢字を使った日常生活の中で身近な話題の文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」というレベルです。つまり、日常会話のスピードがN4レベルの人には早口で聞き取れない場合もあるのです。
また、日本語は漢字の読み方も様々ですし、何気なく使っている言い回しでも外国から来たばかりの人には難しい表現がたくさんあります。たとえば「事故のため、山手線は不通です」と言われれば、山手線を避けて別のルートを探しますよね。ところが、外国から来た人には「不通」が「普通」と聞こえて、通常運転だと理解してしまうこともあるのです。「電車は動いていません」と言い換えれば伝わるのですが、日本語に慣れている人には気づきにくい難しさですね。
もちろん、ゆっくり話せば分かってもらえますし、片言の日本語であっても意味が通じれば十分に働くことはできるものです。「ゆっくりと話す」「分かりやすい表現に言いかえる」など、社内で迎える側の従業員が外国人の同僚に合わせていくことが必要だと思います。
しかし、こうした事情を理解しておらず、従業員に対してN1レベルの「日本で生まれ育った人と同じレベルのコミュニケーションができること」を当然のように求める日本の企業も少なくありません。
――言葉としては通じているはずが、なぜかコミュニケーションエラーが起きるケースもあると聞きます。
日本語自体の難しさに加えて、「日本語でのコミュニケーション」の分かりにくさの問題があります。たとえば「手が空いたらやっておいて」という指示は、言葉通りに受け取るならば、「手が空かなければ(他に取り組む業務がある場合は)やらなくてよい」とも理解できます。しかし、実際は「急ぎではないが必ず着手してほしい」の婉曲表現であるため、数日経ってもまだその仕事に手を付けていなかったら叱られますよね。
「できるだけ早くやって」も誤解を生みやすい指示です。できる範囲でやればいいのかと思いきや、頼んだ側は「最優先で取りかかってほしい」と思っていたりしませんか。
「いいです」「結構です」のような、イエスともノーとも取れる曖昧な表現もあります。相手を思いやり、ていねいな言葉にしたいという気持ちから、あえて直接的な言葉遣いを避けているフレーズですが、外国人との間では意思疎通の妨げになりがちです。「何を」「いつまでに」依頼したいのか、はっきりと伝えるべきでしょう。
「やさしい日本語」の活用を
――日本語に慣れている従業員は、日常会話で特別に「難しい言葉」を使っている意識がないので、何をどう言い換えるといいか迷いそうです。
たとえば、謙譲語や尊敬語を使わないだけでも分かりやすくなります。「召し上がる」を「食べる」に、「土足厳禁」は「くつをぬいでください」と話し言葉に言い換えるとか。
このように、普段よく使う言葉を外国人にも分かりやすく簡単な表現にした日本語は「やさしい日本語」と呼ばれています。工場などで外国人労働者が多く働く愛知県では、県が独自に『「やさしい日本語」の手引き』という冊子を作って啓発に努めています。ホームページから無料でダウンロードできますので職場でも活用してみてください。
雇用契約書や就業規則についても、「やさしい日本語」を使った文章に書き換えて説明するといいですね。漢字はひらがなにして、ふりがなを付けると読まれやすくなります。
――誰にとっても理解しやすい「やさしい日本語」を使うことで、コミュニケーションが取りやすくなるのですね。
「職場の外国人とのトラブル」というと、日本人と〇〇人といった二者間のコミュニケーションの問題を思い浮かべるかもしれません。しかし、今後はそれぞれ異なるルーツを持つ各国の人々が1つの職場で一緒に働くことも珍しくなくなります。お互いがそれぞれの母国語を完璧に覚え合うのは大変です。職場で「やさしい日本語」でのコミュニケーションが普及すれば、外国人同士のコミュニケーションもスムーズになるのではないでしょうか。