パートも社会保険加入へ? 適用拡大の概要と企業が取るべき対応とは
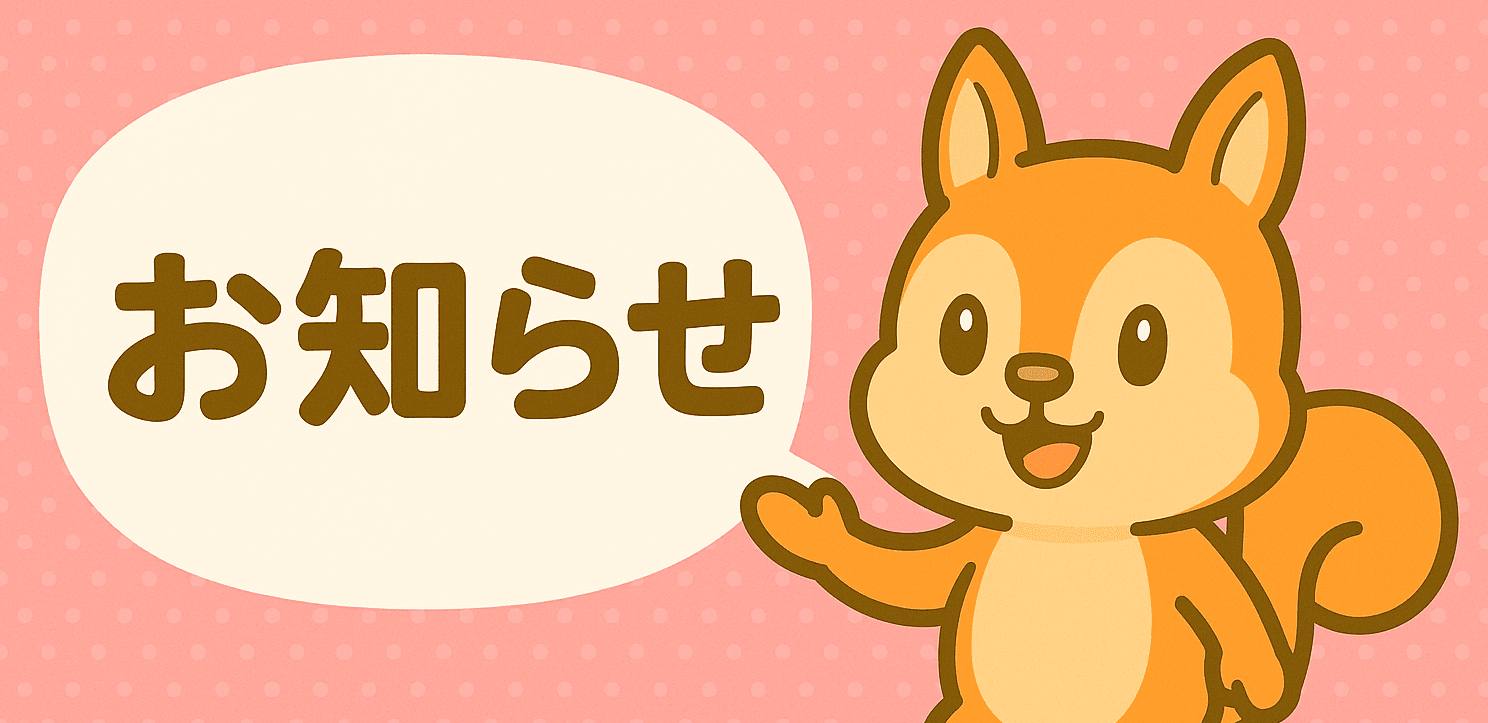
パートも社会保険に加入?
2024年10月からの適用拡大で企業が備えるべきこととは
2022年10月から段階的に進められている社会保険の適用拡大。
これまで対象外だったパートタイマーやアルバイトの方々にも、健康保険や厚生年金の加入義務が広がりつつあります。
そして2024年10月からは、さらに対象となる企業の範囲が拡大され、多くの中小企業でも対応が求められるようになります。
この制度変更により、企業はどのような準備を進めるべきなのでしょうか?
企業が取るべき具体的な対応や注意点をわかりやすく解説していきます。
社会保険の適用拡大とは?
社会保険の適用拡大とは、これまで社会保険の加入義務がなかったパートタイマー等を対象に、段階的に加入を求めていく制度変更です。
| 適用対象となる企業規模 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 従業員501人以上 | これまでどおり |
| 従業員101人以上 | 2022年10月〜 |
| 従業員51人以上 | 2024年10月〜 |
ただし、「従業員数」は厚生年金の適用対象者で判断されます。単純な在籍人数ではなく、フルタイム従業員と、週20時間以上勤務するパート・アルバイト等が対象です。
パートが社会保険に加入する条件(4つすべてを満たす必要あり)
-
週の所定労働時間が20時間以上
-
月額賃金が8.8万円以上
-
2カ月を超える雇用の見込みがある
-
学生ではない(※夜間学生や休学中を除く)
社会保険加入で企業に生じる影響とは?
パートタイマー等が新たに社会保険へ加入することで、企業には以下の負担が発生します。
1. 費用負担の増加
パートにも保険料の**会社負担分(約50%)**が発生します。
試算例:
-
時給:1,072円(東京都最低賃金)
-
月88,000円の給与 → 保険適用対象に
-
会社の負担:
-
健康保険料 約4,316円
-
厚生年金保険料 約8,052円
-
合計:1人あたり約12,368円/月
-
10名雇用で年間約148万円のコスト増となります。
2. 手続き業務の増加
-
加入手続(資格取得届、算定基礎届、賞与支払届 など)
-
給与からの保険料控除
-
月額変更届・算定基礎届の作成・提出 など
3. 人材確保への影響も
-
社会保険に入りたくないと考えるパートからの離職
-
新規応募の減少
-
一方で、「保険加入可」を魅力に感じる層の応募は増える可能性も
対応に向けて企業がすべき9つのステップ
-
法令の正確な理解
厚労省の特設サイトや社労士への相談が有効です。 -
自社が適用対象か確認
「フルタイム+週20時間以上のパート」が51人以上いるか。 -
新たに対象となる従業員の把握
該当者の労働時間・賃金・雇用期間・学生かどうかを確認。 -
人件費のシミュレーション
厚労省の「かんたんシミュレーター」で試算が可能。 -
書式・規程の整備
雇用契約書や就業規則に社会保険の内容を明記しましょう。 -
従業員への丁寧な説明
説明会・個別面談で誤解や不安を解消。 -
社会保険の加入手続き
日本年金機構の情報を参照し、対象者を正しく申請。 -
給与計算システムへの反映
保険料を給与から正しく控除・納付する体制を整えます。 -
定期的な手続(算定基礎届・月額変更届)の実施
制度運用後も定期的な管理が必要です。
まとめ:準備がトラブル防止のカギに
社会保険制度の拡大は、働き方や雇用制度の見直しが必要になる大きな変化です。
制度の正しい理解と早めの準備が、企業と従業員の双方にとっての安心につながります。
不安な場合は、社会保険労務士や日本年金機構の「適用拡大相談チャット」を活用しましょう。